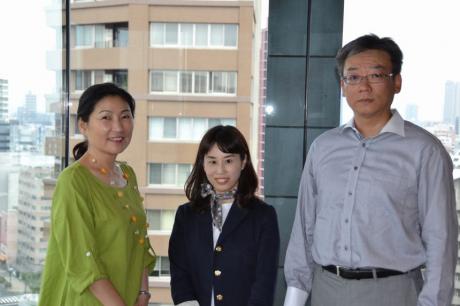大阪弁護士会広報室の加藤慶子です。
本日は,「広報室,こんなことしていますシリーズ」の記事をお送りします。
当広報室は,定期的に司法記者クラブとの交流の場を持っており,
毎回著名な弁護士のゲストを記者と広報室とで囲む「居酒屋広報室」や
弁護士会からの広報関係を伝える「司法記者クラブとの昼食会」などを開催しています。
そして,先日,新企画「なるほど!広報室」の第1回目を開催しました。
「なるほど!広報室」は,昨今話題の法律改正・社会問題について,
短時間でその途のプロフェッショナルの弁護士から
お得に学んでいこうという企画です。
今回のテーマは「マイナンバー制度」です。
講師は,坂本団弁護士でした。
坂本弁護士は,日弁連の情報問題対策委員会委員長を務められており,
衆議院で参考人として意見を述べたり,
日本記者クラブを初め各方面からの取材を受けたりしている方です。
ちなみに,愛読書は,『ハッカージャパン』(ただし,休刊中)とのことです。
![]()
「マイナンバー制度」について,
私自身は恥ずかしながらよく分かっていなかったので・・・
いろんな「ふむふむ,なるほど!」を勉強させてもらいました。
まず,漏えいの問題・・・
10月以降,各世帯に「マイナンバー」が届きます。
そして,その番号を勤務先に提出することになるということです。
ということは,零細な民間事業者も含めて
個人番号を取り扱うことになりますが,
全事業主が規制の内容を正確に理解し,
取り扱いを徹底することは,ほぼ不可能と見込まれます。
先日情報漏えいがニュースとなった
公的年金業務を取り扱う日本年金機構においても,
「平成24年度~平成26年度の過去3年以内において,
個人情報の本人の数が101人以上となる重大事故を
11件発生しており,8772名に影響を与えることとなった」が,
「再犯防止対策は十分に行っている」と宣言していました。
次に,なりすましの問題・・・
マイナンバーは民と官とが情報連携をするために付されるものですが,
そのためには,正確に本人確認が徹底されることが不可欠です。
ちなみに,米国では社会保障番号を悪用した
深刻ななりすまし被害が発生しているということでした。
(2006年~2008年までの間に,
被害件数1170件,被害額約500億円)
ただ,本人確認を徹底しようとすると,
番号の提出を受けることができない
=源泉徴収できない(国からすると税金が取れない)
という不都合が生じます。
よって,住民票等の原則的な書類の提出が困難な場合には,
その本人確認書類として,
「自身の個人番号に相違いない旨の申立て申立書」でも
認められているということになっています。
・・・これで良いのでしょうか。
そして,適用除外の問題・・・
番号法は,刑事事件の捜査,反則事犯の調査には,適用されません。
すなわち,個人番号を利用して捜査を進めることは適法で,
令状も何もいらないのです。
これが現実に,来年の1月から,個人番号の利用が開始が始まります。
問題だらけの「マイナンバー制度」だと思いました。
記者の方々からも素朴で鋭い質問が多数寄せられましたが,
坂本弁護士がさらさらと回答されていました。
さてさて,懇親会の場では,さらに盛り上がりをみせ,
記者の方々の関心や,ピンときているネタとも含めて
いろんな意見交換がありました。
また,今年の6月まで日弁連の機関雑誌『自由と正義』の編集長であった
高橋司弁護士の参加もあり,『自由と正義』の編集話なども聞けました。
本当に,広報室の仕事を通じて私自身が色々と勉強させてもらっています。
次の「なるほど広報室」も,期待が高まります。